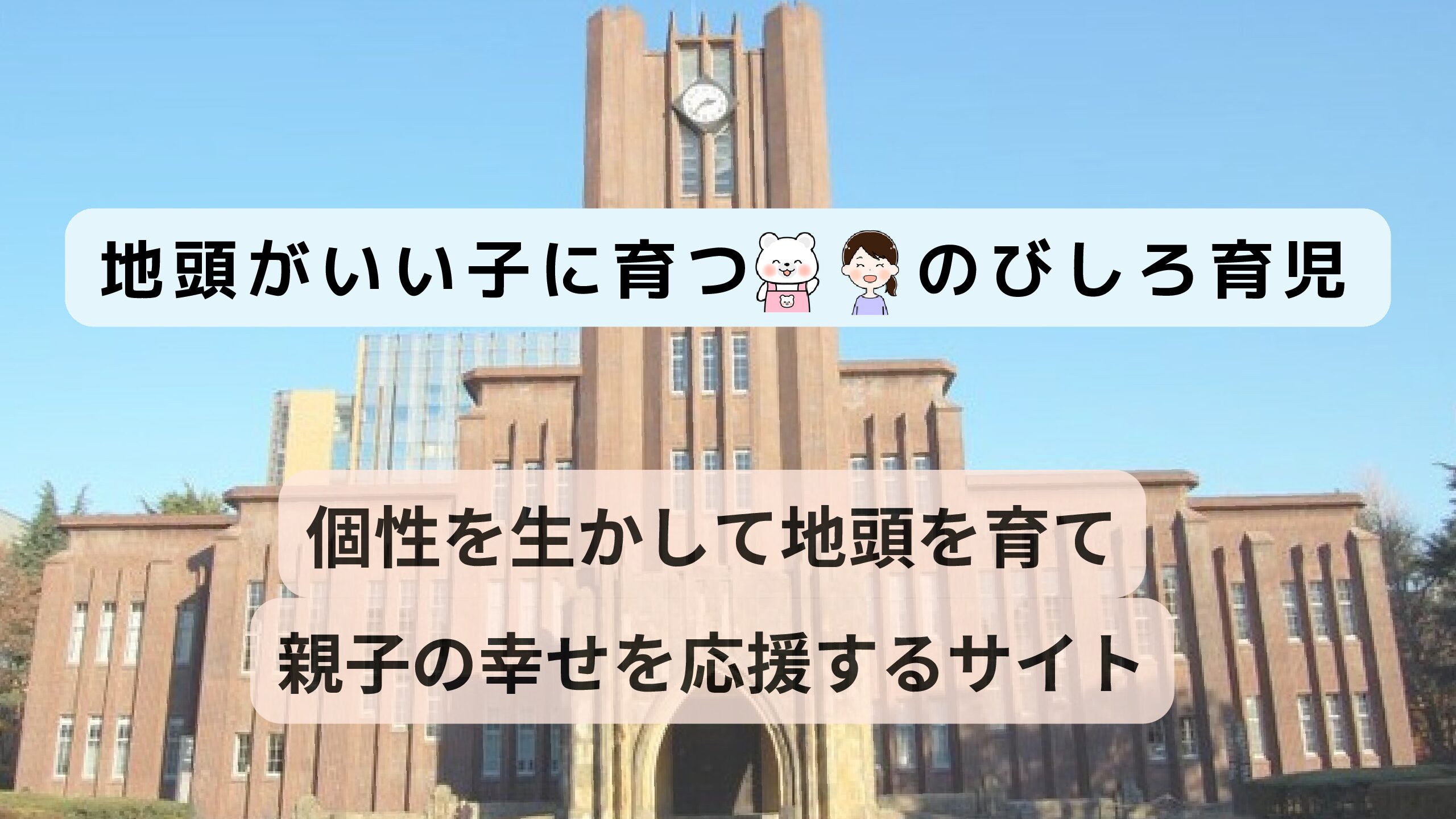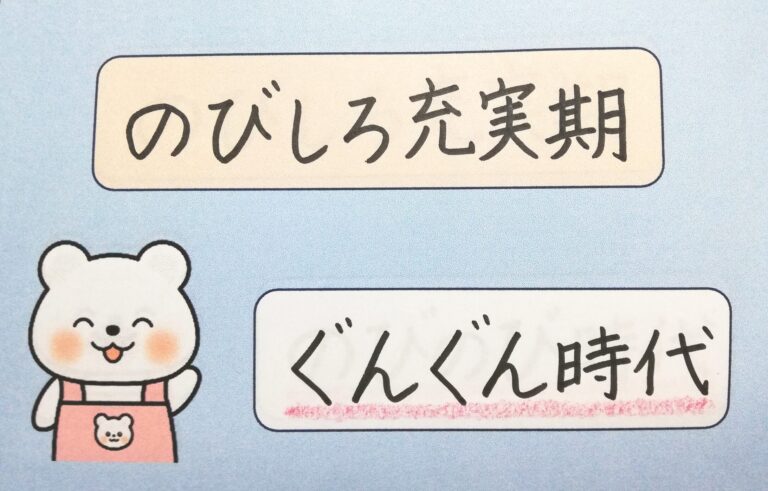①こんな様子
・社会性が育ち、人と関わって遊ぶことを楽しむ。
・興味が広がり、熱中することが増える。
・自分なりにルールや遊び方を工夫する。
・ドリルなどに興味を持ち、進んで学習しようとする。

②こんな働きかけを
○工夫して遊べる余地がある素材を、たくさん身近に置く。
○家族や友達と楽しめる、ルールが簡単なボードゲームを用意する。
○子どもが熱中しているもの、興味のあるものが分かったら、それを広げられるような環境を用意する。
この時代の子どもは、自分からぐんぐん興味を広げ、工夫し、進んでいきます。
ぜひその姿を応援してほしいと思います。
家族や友達と一緒にボードゲームやトランプなどで遊ぶのも、とても楽しむ時期です。
探せば楽しいボードゲームはたくさんあるので、親子の楽しいひとときにとてもおすすめです。
遊びながら、負けても次がある、という気持ちを育てることもできますよ。

③こんなことに気をつけて
このような環境を作ると、必然的に片付いた状況を保てなくなってきます。
きれい好きのママとしては、気になって、
遊ぶたびに片付けさせたい気持ちになりますよね。
でも片付けを考えて遊ぶような遊び方を、のびしろ育児では勧めていません。
脳をのびのびさせて、熱中して遊ぶからこそ、集中力が育まれるのですから。
ですからこの時代は、「仕方ないな」と片付けにはちょっと目をつぶって、
親子共々楽にいきましょう。
子どもたちを育てて20年以上も経っている私からすると、そんな時代はほんの一時ですよ。

④のびしろ家では
のびしろ家の子どもたちが熱中したのは、ままごと、工作、ボードゲームなどなど。
見立て遊びに使うために、さまざまな色ホースを切ったものや、
さまざまな色のシフォンスカーフなども用意。
徹底的に、楽しく遊べる環境を作っていました。
子どもたちはあらゆる遊びに熱中しましたが、
一番散らかる原因になったのは、工作のために切った後に残った紙、でした・・・。
(さすがにこれだけは定期的に、「残った紙、捨ててね」と言っていました)
のびしろ家では、よくあるお絵かき帳ではとてもお絵かきや工作に足りなかったので、
A4サイズのコピー用紙を束で購入し、それを使わせていました。
はさみと紙と、それからセロハンテープ。
その3つがあれば、作りたいと思った、ありとあらゆる物を工作していた我が子たち。
そして自分たちが作った物を使って、楽しそうに遊んでいました。
今思えば、3人とも数学が得意で、立体問題にも全く苦労しなかった理由は、
このあたりの遊び方にあったのかもしれません。